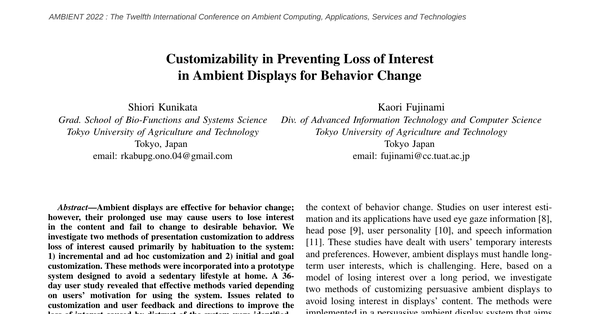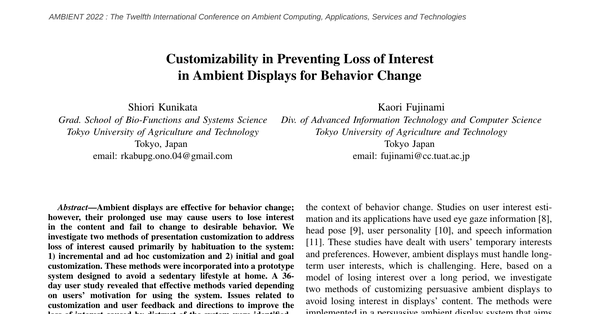<< TOPへ
Customizability in Preventing Loss of Interest in Ambient Displays for Behavior Change
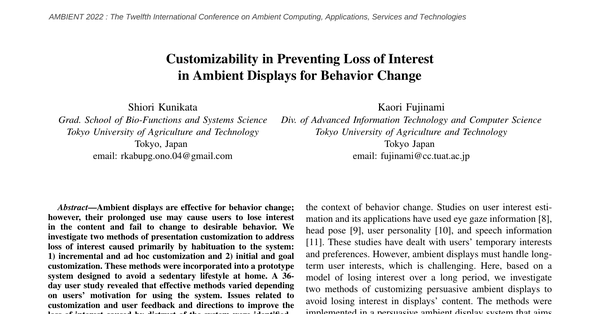
・環境ディスプレイを用いた行動変容における興味喪失を防ぐためのカスタマイズの研究。2022年。
・多分、コロナでおうち時間が増えたので、運動量を増やすための動機付けを行いたいことが目的で、その動機付けのための対象者の行動計測(Wi-Fiアクセスポイントと、Fitbit)と、環境ディスプレイによる対象者へのフィードバックと、行動の増加を目的としている。
・フィードバックの仕方をいろいろと健闘しているけれども、対象者の興味や動機付けのレベルによってそのカスタマイズの効果は異なってて、いろいろ戦略を練らなきゃねって結論。
・「トランスセオレティカルモデルの行動変容」の段階を推定することを試みてきた、とある。
・トランスセオレティカルモデル(TTM: Transtheoretical Model)は、人が行動変容を遂げる過程を説明する心理学の理論のことらしい。ジェームズ・プロチャスカとカルロス・ディクレメンテによって1980年代に開発されました。TTMは、人が行動を変える際に、いくつかの段階を経ると提唱してる。以下。
前考慮期(Precontemplation):変化の必要性を認識していない、または興味がない段階。
考慮期(Contemplation):変化の必要性を認識し始め、将来的に変化を考える段階。
準備期(Preparation):変化をする意志があり、近い将来に行動を起こそうとしている段階。
行動期(Action):実際に新しい行動を取り入れている段階。
維持期(Maintenance):変化を維持し、元の行動に戻らないように努めている段階。
終了期(Termination):新しい行動が完全に定着し、元の行動に戻ることがない段階。ただし、全ての行動変容においてこの段階が適用されるわけではありません。
・消費者の購買モデルのAIDMAを思い出した。
・そして、そのTTMに基づいて動機付け戦略を変更することで、行動を促進すること。 決定木分類器を用いて動機段階を推定することも可能だといってる。
・相手に応じた意識啓発方法と考えると、とても納得いく。無駄がないよね。
・障害者の就業や作業に対するモチベーション確保などに関係するかな。
https://www.thinkmind.org/index.php?view=instance&instance=AMBIENT+2022
![]()
1 / 1